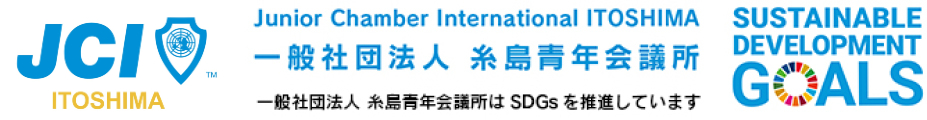所信
はじめに
約10年、私は糸島青年会議所(以下、糸島JC)という学び舎で多くのことを学ばせていただきました。その中で、この糸島JCに脈々と受け継がれている、目に見えぬ力の存在を強く感じています。それは、「何が何でも糸島をよくしてやろう」という熱量の存在です。この熱量の正体は一体何なのか。それは、遡れば糸島JCの発足当時、さらにたどれば戦後復興に立ち上がった先人たちが、まちのために掲げた志であると私は考えています。腹の底から湧き出るようなこの感覚は、目には見えぬとも、まちを想う同志たちとともに汗を流し、時間を共有することで受け継がれてきました。熱量がもつ力、それはどんな状況下においても突破口を切り拓き、物事を前へ推し進める力、推進力です。まちの発展には推進力が必要であり、その原動力となる高い熱量をもち合わせた人がどれだけいるかで、まちの強さは決まってくると思います。そんな熱量を絶やすことなく、もっと高め、もっと広げていく必要があると強く感じています。では、熱量を高めるために必要なことは何なのか。それは、夢を描くことであると考えます。我々は「明るい豊かな社会の実現」という大きな夢を掲げ、その実現に向けた過程を事業化しています。その一つひとつの事業が掲げるめざすべき姿、ゴールに向かい、我が事として取り組む姿勢が個々の熱量を高めていくと考えています。そして、一人でも多く高い熱量をもち合わせた人を増やすために、インパクトある事業を通し我々の熱量をまちの人々へと伝播させることで、この糸島地域に新たな火を灯します。
我々の存在意義は、「何が何でも糸島をよくしてやろう」という熱量とともに「我々にしかできないことをやる」ことであると考えます。我々がもち得る最大限の熱量を糸島地域のために注ぎ、我々が糸島地域の推進力となることで、その結果は、巡り巡って日々の豊かさにつながっていきます。すべてのはじまりとなる変革の起点は「自分自身が変わること」です。この糸島を、何が何でもよくしてやろう。誰もが笑顔で夢を描ける、そんな「明るい豊かな社会の実現」をめざして。
熱量の襷
今後、人口減少や少子高齢化が進もうとも、熱量高くまちの未来について考え積極的に挑戦する人が増えれば、そのまちは活力に溢れ光り輝き続けるのではないでしょうか。そのためにも、まずは我々が「社会により良い変化をもたらす青年」として、糸島の推進力であり続けなければなりません。しかしながら、個としてのJC 活動には40 歳で卒業という制限があります。その制限の中で使命を全うし続けるにはどうしたらよいのでしょうか。その答えは、熱量の襷を次の世代へとつないでいくことです。そのためには、常に新しい力を迎え入れる運動「会員拡大」と、糸島JC がその新しい力に対し、「社会により良い変化をもたらす青年へと成長するための機会」を提供できる団体であり続けることが必要不可欠です。
各地のJC が会員減少に頭を抱えています。糸島JC も例外ではありませんし、それはどの組織においても共通の課題ではないでしょうか。そもそも、JC は40 歳定年制のため会員拡大を行わない限り組織が衰退の道を歩むのは明白です。この特性をメンバー一人ひとりが認識した上で、常に我が事として会員拡大に取り組む必要があります。そのためにも、会員拡大に対する会全体の熱量をいかにして高め続けるかが重要です。まずは、メンバー一人ひとりがJC を深く知り、JC の魅力を説明できる様に、JC の理念と存在意義をLOM 内に浸透させる必要があります。その上で、一人ひとりが取り組む会員拡大の進捗や、会員拡大の手法に関するアイデア、拡大対象者の情報についてメンバー同士が語り合う環境を意図的かつ定期的に設け、メンバー全員の会員拡大に対する意識を途切れさせない工夫が必要です。そして、会全体で取り組む会員拡大の進捗と結果をメンバー全員で常に共有し、糸島JC 一丸となって試行錯誤を繰り返すことで、糸島JC 内に大きな会員拡大ムーブメントを巻き起こしましょう。「明るい豊かな社会の実現」に辿り着くその日まで、熱量の襷を途絶えさせてはなりません。
「出逢い」の数の多さはJC の大きな魅力の一つです。しかしながら、この機会は受け身で待っていては一向に増えませんし、ただ知り合っただけでは「出逢い」とも呼べません。自らの足で動き、ともに汗を流し、苦楽をともにした仲間との縁こそ、そう呼べるのではないでしょうか。人となりは、その人の「出逢い」の量と質で構築されていくものであると考えます。その人が歩んできた人生や経験もまた、生きてきた環境、即ちその人がどのような人たちと時間を共に過ごしてきたかということです。JC には、やる気と希望、そして気概に満ち溢れたメンバーが多く存在します。JC とは、そういったメンバーとの「出逢い」により、自分という存在を高め続けることができる唯一無二の場所であると考えます。戦後復興に立ち上がった先人たちより脈々と受け継がれている熱量の襷も、幾多の「出逢い」によって今我々の手元にあります。この「出逢い」を求める過程に、挑戦と修練が伴うこともまたJC 特有の魅力です。そして、この言葉には運命的なニュアンスが含まれています。文字通り、JC で得られる「出逢い」は一生ものばかりです。この一生もののつながりは縦にも横にも広がり、そのつながりは、強く魅力的なまちをつくります。未だ見ぬ新しい力との「出逢い」を求め、会員拡大運動を推進してまいりましょう。
夢を描く
リーダーの仕事とは「夢を描くこと」であると考えます。それも、ちょっと頑張れば手が届きそうなものではなく、現状の外側にあるような大きな夢です。そして、その夢に向かい行動を起こし続けるには、夢に対する圧倒的な臨場感が必要です。臨場感とは、その夢を達成できると思える「根拠なき自信」によって形成される感覚であると考えます。考えてみると、この世界の大半は「根拠なき自信」から生まれたもので成り立っています。人類が月に行けた理由は、月に行きたいという大きな夢と、月に行ける気しかしないという「根拠なき自信」をもった集団が過去にいたからではないでしょうか。我々も「明るい豊かな社会の実現」という大きな夢を掲げ、自分たちにはできると強く信じ、その実現に向けた過程を事業化しています。そして、我々だけではなく、まちの人々が「糸島はもっとよくなる、もっとよくできる」と心の底から思い、自発的に行動を起こすためのきっかけを、我々はまちのリーダーとして提示し続けていく必要があります。そのためにも、まずは我々一人ひとりがまちの未来を見据え、大きな夢を描きましょう。夢に向かう道、それはとても険しく、挑戦の連続です。それでも、夢に向けた挑戦に没入することで、そこから得られる「自ら挑戦した」という経験は、明確な自信へとつながります。その自信が夢の臨場感をさらに高め、次の行動へとつながり、こうして生まれるサイクルこそが、まちにとっての持続可能な推進力であると考えています。JC では、このサイクルを生み出す仕組みを「単年度制」という短い期間の中で繰り返し経験することが可能です。この仕組みは、先人たちの手によって整えられたJC における特筆すべき学びの機会であり、JC に身を置くのであればこの環境を大いに活用し、我々一人ひとりが「夢を描ける」まちのリーダーと成るべきです。この成長は我々の責務であり、我々の成長がまちの未来をつくります。そして、この成長こそが、我々が生まれ育ったまちと、我々のJC 活動を支えてくれている方々への恩返しです。変革の起点は「自分自身が変わること」です。貪欲に成長の機会を追い求め、夢を描き、夢に向かい前へ進み続けましょう。
糸島の未来をつくる
糸島市は、福岡市との交通の利便性や豊かな自然と農林水産物、歴史・文化に恵まれている場所です。近年では、メディアで取り上げられる機会も多く、市外から多くの人々が訪れています。そんな「糸島ブランド」とも呼ばれる現在の姿も、一朝一夕で成せたことではありません。糸島の未来を想い、各分野で汗を流された先人たちの集大成が「今」の糸島の姿です。先人たちが糸島の未来に込めた想い、それは、自分の大切な人たちが住み暮らす糸島をもっともっと素晴らしい場所にしたい、そして、大切な人たちに、この先も糸島で幸せに暮らして欲しいという願いであると私は考えています。我々、糸島JC も「私たちが住み、そして子らが住み、私たちの子孫が営々として住むであろうこの糸島をもっともっと愛し、美しく素晴らしいものにしたい」そう志を掲げ、48 年間、糸島の未来を見据えた運動を展開してまいりました。先人たちより熱量の襷を受け取った「今」を生きる我々も、糸島の未来を想い、糸島の未来に花咲く新たな種をまき続けなければなりません。そのためにも、糸島の課題を先見的に捉え、先駆けて取り組み続ける必要があります。
まちをかたちづくる大きな要素は「人」であると考えます。その中で子供の存在は、まち
の未来そのものと言っても過言ではありませんし、地域における子供の活躍は「元気なまち」を象徴する一つの理想的な姿であると考えます。子供の存在は、周りの大人、さらにはまち全体をも動かす大きな力をもっています。そんな子供たちが、まちの第一線で活躍する世代となった時に「まちを想い、まちにより良い変化をもたらす青年」へと成長していたら、そのまちはとても強く、活力に溢れ光り輝き続ける魅力的なまちです。そのためにも、子供たちの「愛郷心」と「まちを誇りに思う気持ち」を育むことができる機会を提供し、子供たちが自分たちの住み暮らすまちに興味や関心、愛郷心と誇りをもって、意欲的に自らまちづくりに参加することができる姿勢を養う必要があります。また、まちがより良く成長し続けるためには、いつの時代においても地域経済の発展が必要不可欠です。まちの未来を担う子供たちの興味や関心を糸島の経済発展に向けることができたら、未来の糸島には、まちの発展における本質的な分野で「まちにより良い変化をもたらし続ける青年」が多く存在していると考えます。そのためにも、子供たちの「経済感覚」を養い、大人と子供が知恵を出し合い、地域を巻き込みながら糸島の経済発展を推進することが重要です。前述したどちらの要素に関しても、子供たちにとって大きなインパクトとして心に遺り続ける体験として我々が創出すべきです。そして、地域経済を発展させるには「地域の価値」を高め続ける必要があります。多くの自治体が、地域のPR や特産品の販路開拓、新商品の開発に取り組み、地域の経済活性化「地域ブランドの推進」を図っています。糸島市においても「いとしまブランド推進計画」が策定されており、既存の価値は自治体によって常に増強が図られています。そんな状況下において我々がなすべきことは、現状の外側にあるような大きな夢を描くことです。誰もがイメージできる範疇のことを我々が行っても、まちに大きなインパクトをもたらすことはできませんし、多種多様な視点で市民意識変革運動を推進する我々の存在意義が果たせません。我々にしかできない穿った見方と斬新な切り口で、糸島の未来に花咲く「新たな価値」を「今」我々が先駆けて創出すべきです。さらに、我々が創るインパクトが「単年度制」に捉われることなく、まちの人々の意識を変革し続けるためには、その新たな価値が糸島のムーブメントとして、まちの未来に対する影響力をもち続ける必要があります。
「今」まくべき未来への種は、我々がまちのリーダーとして糸島に掲げる大きな夢です。夢の実現に向けた挑戦は地域を巻き込み、まちの人々の共感を生み出します。その過程で糸島全体へと伝播する我々の熱量は、必ずや糸島を明るい豊かな未来へと導く大きな推進力になると信じています。そして、我々が創出する未来への種のまき方は、日本各地においても同様の効果をもたらすことが可能なモデルケースとなり得ます。糸島から日本を変える決意をもって、まずは我々が糸島の未来をつくりましょう。
創立50 周年に向けて
1977 年、糸島の未来を「美しく素晴らしいものにしたい」と強く願う青年たちの手によって糸島にJC の火が灯りました。そして、今日に至るまでの48 年間、糸島JC はどんな時代においても「社会により良い変化をもたらす青年」が集う団体として、先見的な姿勢をもって社会課題の解決に取り組み続けています。先輩諸兄姉の「何が何でも糸島をよくしてやろう」という熱量と弛まぬ努力、その中で生まれた幾多の「出逢い」により縦と横に
広がった人と人とのつながりが、確実に「今」の糸島をつくっています。2026 年、糸島JC は創立50 周年という大きな節目を迎えます。本年度は、その来る日に向けた準備を整える大切な年です。我々が当たり前にJC 活動に取り組むことができている「今」は、これまで先輩諸兄姉がその時々の課題と真剣に向き合い行動した「過去」の結果です。まずは「過去」に触れ、感謝の念を抱き、我々の誇りを心に刻み、託されたものをつないでいく覚悟をもちましょう。そして、2021 年に策定した「糸島地域持続化宣言」の検証を軸に据え、我々が「未来」に向けてなすべきことを検討してまいります。これまでとこれからを追求することは、「今」を生きる我々の責任をより明確に捉える絶好の機会です。いずれ「過去」となる「今」を、「未来」に最良の結果を残せる時間とすべく、糸島JC メンバー一人ひとりが「今」なすべきことを自分自身に落とし込み、その決意とともに高まる熱量を糸島のために注ぎ続けましょう。
結びに
熱量を高めるために必要なことは、何事にも我が事として取り組む姿勢です。その姿勢をもって、常に勇気を伴う一歩を踏み出し続けることで「自分」という存在の可能性は無限に広がり続けると知りました。勇気を伴う一歩とは、現状の自分では背伸びしても手が届くか届かないか分からない試練に挑戦すること、つまり、その挑戦に伴う不安や負荷を受け入れる覚悟をもつということです。このことを教えてくれたのは、糸島JC です。そして、広がる可能性を糸島のために役立てたいと強く思う度、自分の熱量が際限なく高まることも教わりました。同時に、「生きる上で注ぐことができる熱量の最大値は100 ではない」ということも学びました。仮に仕事とJC のみで100 の配分を考えるのならば、どちらかが100 となった場合にもう片方が0 になるのではなく、どちらも100 にして、最大値を200 にするという姿勢です。どちらかの度合いが高まれれば、もう一方の度合いも高め、常に自分自身の中で切磋琢磨し続けることで、個人がもつ熱量は際限なく高まります。前述の姿勢を全うするために重要なことは、24 時間という全ての人に平等に与えられた時間というものをどのように使うかということです。その使い方には「決断」が常に伴います。文字通り、「断つことを決める」ということです。メンバー一人ひとりが何事にも我が事として取り組む姿勢をもって自分自身と向き合い続け、それぞれの変化が訪れた時、我々は糸島の「変革の起点」と成っています。
いつの日からか、寝ても覚めても「何が何でもよくしてやろう」という気持ちが消えません。その対象は、住み暮らす糸島地域のこと、糸島JC のこと。もちろん、社業や家族、私を応援してくれている方々に対しても同様です。こんな自分に育ててくれた糸島JC との出逢いに心から感謝しています。そして、この熱量を絶やすことなく、もっと高め、もっと広げていく必要があると強く感じています。まちに住み暮らす一人でも多くの意識が変わり、一人でも多くの熱量が高まれば、「明るい豊かな社会の実現」に手は届くのではないでしょうか。そうするべく、我々がいるのです。我々はまだまだ30 代前後の若造です。若造らしく、泥臭く、直向きに、我々にしかできないことをやろう。この糸島を、何が何でもよくしてやろう。熱量高く、まちの推進力となれ。
2025年度 一般社団法人 糸島青年会議所
第49代理事長 松吉 孝達
顧問 田中 宏明
<執行部>
直前理事長兼監事 中村 信就
監事 牛原 令資
副理事長 河野 伸二
副理事長 仲原 央隆
副理事長 浦山 浩
副理事長 松山 将大
専務理事 松﨑 治久
常務理事 旭 真輝
【基本方針】
・会員同士の絆と思いやりを大切にした組織運営
・規律ある例会の運営による会員の相互交流と資質向上
・持続可能な地域を共にめざす志高き会員の拡大と育成
・事業効果を最大限に高める戦略的な広報活動の展開
・行政を含む他団体とのパートナーシップの構築
・志を同じくする他団体と連携した協働のまちづくり事業の実施
・糸島地域の次世代を担う青少年の健全育成事業の実施
【事業計画】
(1) 一般社団法人糸島青年会議所として理事長所信に基づいた、運動・ 事業で委員会が行うもの
(2) 福岡ブロック協議会、九州地区協議会、日本青年会議所、JCIが主催する事業で、連携または依頼されたもの
(3) 糸島地域の各団体が主催する事業で、豊かな糸島の創造につながるものへの連携・協力
【各役職務】
定款第5章 第29条から第34条並びに第36条による。
上記事業計画(3)については適宜、組織編成を行い連携・協力する。
【職務分掌】
〇全委員会共通
・例会に関する事項
会員の相互交流と資質向上の機会および規律ある例会の企画・運営
(各委員会は年12回の例会うち3回を企画・運営)
・糸島地域持続化宣言に則した事業の実施
・各種事業への積極的な参画
・出向者支援
・会員拡大の推進と新入会員のフォローアップ
〇まちの未来創造委員会
・「新たな価値を創出する」まちづくり事業の実施
・「愛郷心、糸島への誇り、経済感覚を養う」青少年健全育成事業(糸島塾)の実施
・社会福祉法人糸島市社会福祉協議会との連携に関する事項
・例会に関する事項(2月、6月、11月)
〇会員拡大委員会
・会員拡大の中心的な役割の遂行
・新入会員のフォローアップと育成
・新入会員による新入会事業の企画・実施(10月度例会)
・各種懇親会時の一部を活用した拡大戦略ミーティングの実施
・会員拡大の推進と新入会員との積極的な交流
・例会に関する事項(1月、4月、10月)
・糸島駅伝大会の運営および青年団体連合会への協力
・第3エリア野球大会に関する事項
・じゃがいもゴルフコンペの企画と運営
・献血事業の実施協力
〇総務広報渉外委員会
・総務に関する事項
総会の設営並びに運営(1月、9月、12月)
定款・諸規定の見直しおよび名刺・会員手帳の発行
理事会等の議案配信
褒賞エントリーへの取り組み
議案ライブラリーの管理
理事会等におけるアジェンダの作成と配信
アジェンダシステムの導入検討
・広報に関する事項
ホームページの運営・効果的な対内外へ向けた情報の迅速な共有と発信
・渉外に関する事項
出向者支援
・第9回糸島わんぱく相撲大会の企画と実施
・例会に関する事項(8月、9月、12月)
〇50周年準備委員会
・50周年に向けた準備に関する事項
・糸島地域持続化宣言の検証
・4団体による新春祝賀会行事の運営協力
・一般社団法人唐津青年会議所との交流に関する事項
・例会に関する事項(3月、5月、7月)
〇執行部
・Googleカレンダーの管理